先日、とあるチームに移籍をしました。今は移籍のルールみたいので試合に出れていないのでチームなどはまた後日発表したいのですが、ニュージーランドからオーストラリアのチームに移籍をしました。既に練習や練習試合に参加していて、新しい環境に来た緊張感やわくわくのなかで生活しサッカーをしています。
そんな中で1つ気付いたのですが、国を変えてチームも新しくなったはずなのに、どこかやりにくさというか違和感がそこまで大きくないことに気が付きました。その理由のひとつにに「英語」というものが浮かび上がりました。
NZに来た頃と比較して最も変化したのは語学力。同じ英語を話すこの国では、チームについてからの流れや練習中に監督が言っていることもほぼほぼ理解できる状況にあります。しかし、僕がNZに乗り込んだ二年前はそうではありませんでした。
つまり「新しい環境でサッカーをすること」と「外国でサッカーをすること」そして「言葉の違う国でサッカーをすること」はイコールではないということです。
今現在、英語が世界で一番話されている言語である事からももしかしたら今後同じような体験はしないかもしれません。そう考えると、言語の分からない環境でサッカーをするということはとても貴重だったものになります。そして、ここで考えをまとめておくことは、今後もし訳の分からない国でサッカーをすることになった時にも役立ちそうなので振り返ってみたいと思います。
(オーストラリアのAdelaideに引っ越してきたのでAdelaideの写真と共に振り返っていきます。)
ニュージーランドに来た頃に感じたこと

まずはじめに僕がニュージーランドに来た頃に感じたことや当時の状況について軽く振り返りたいと思います。
想像以上に伝わらなかった英語
ニュージーランドにきてからの一番の印象は英語がほとんど通用しなかったことです。自分なりに勉強していったつもりなのですが、まあ甘かったです。たしかに生きていくだけの英語というか、家を探したり買い物をするにはなんとか伝わるんですが、相手からとっさに何かを要求されるような場面には答えることが出来ていませんでした。
サッカーの時はどうだったかというと、これもまた難しかったです。僕はいきなりニュージーランドに乗り込んである種の道場破りのような形で練習参加していたので、チームに入るためには「自分を売り込むこと」が大切でした。
プレーで売るのはもちろんのことですが、プロではないこともあり「いい奴」だと思われることが大切だと思っていました。
しかし、そのための人間関係作りというかコミュニケーションにおいてまだまだだったなと思います。幸い、親切なチームメイトに恵まれ結局同じチームで二年半過ごすことが出来たのですが。
コミュニケーションが取れない中でのサッカーについて
まずサッカーにおけるコミュニケーションにはざっくり3種類あると思います。
・Listening
・Speaking
・Body Language
それぞれについて考えていきたいと思います。
Listening
サッカーにおいて聞くという作業はとても大切に思います。監督からの指示や仲間の要求を聞くためです。チームには戦術があって、それを正しく理解して実行しなくてはチームにエラーが生じます。その原因となっては「使えない選手」になってしまいます。そうならないためにも「聞く」という能力は大切でした。
先に述べたように、当時の僕のリスニングレベルは論外です。包丁の使い方も知らない料理人のようなレベルでした。
ですが以外にも振り返ってみると、当時から監督の指示やハーフタイムの話し合いはだいたい理解できていたように思います。その理由は「サッカーの局面からある程度予測が出来たから」です。
日本似た頃からそうでしたが、プレーしている時もそうでないときも「どうすればチームが良くなるか」課題や解決策を自分なりに考えるようにしていた事が功を奏し、未知の言語を話す彼らの内容をある程度推測出来ていました。これは英語が話せなくてもホテルのチェックインが出来たり、入国審査を突破できるあの感覚そのものです。
その場の状況から予測できるというのはサッカーにおいてかなり大きかったです。
ですが、試合中にチームメイトに言われるこまかい要求については正直10%くらいしか理解していなかったです。ただでさえ聞き取れないのに試合中のあの熱量で言われるともっと分からないし、その上聞き返してる時間もないので「Okay,okay」といってその場を濁していました。
一番難しいのはトレーニングの説明です。デモンストレーションなしで言葉のみでの説明は僕にとって地獄でした。ゲームの制限などもよく理解出来ていないままスタートしてしまうので、「How many touches?」と最低限のタッチ数を把握してあとはプレーしながら周りを伺い理解するようにしていました。
総じて、聞き取れているか?と言われると30%にも満たないような状況でしたが、予測が大きなサポートとなってサッカーに必要な理解力は満たしていたように思います。
どれくらい自分が理解していると思っていたことがあっていたのかは分かりませんが、一度スタメンを獲得してからは外れることもなかったし、チーム退団時には「Smart」なプレイヤーとして認識されていたので、僕の読みはさほど間違っていないように思います。
Speaking

当時の僕のリスニング能力の低さを晒しましたが、スピーキングはそれをはるかに凌ぐひどさでした。包丁すら持っていない状況でした。
ですがサッカーとなると話が変わりました。意外にもプレー中に伝えるという行為は言語が変わっても自然に出来ていました。というのもサッカーのプレー中というのは常に状況が変わり「時間」も限られています。そんな中で伝えるために必要最低限の言葉は「単語」になってきます。極論、これで伝わるのがベストです。
例えば「Now, Here, Go,,,」こんなとこです。アホみたいに簡単な単語たちですがサッカーのプレー中に使われるこれらワードの重要度と威力は抜群です。逆にこれが話せない選手は使えないというくらいです。
他にもトラップをTouchと言ったり、足元をFeetと要求したり、こっちに来てプレーしてみなくては知らなかったワードもありましたが一度知ってしまえば使いこなすのは簡単でした。
これが自然とできていたこともあり、サッカーにおける伝えるという能力の50%はクリアしていたようにおもおもいます。
ですが、残り半分がとても難しいところで今でも苦労しています。
1つは戦術的な会話や議論です。ボードがあればなんとか出来ますが、今でも口頭のみで僕がイメージしている状況を伝え、要求するのは難しいしうまく伝わっていない感があります。特に時間のない試合中に伝えるのは今でに至難の業です。最初はそれでもトライしていたのですが、いつからか僕はあまり伝えないようになってしまいました。伝える事でチームに与えるメリットよりも、コストの方が大きいと感じるようになったからです。これはあまりよくないことで今後の課題でもありますが、その結果得られたメリットがあることにも気付きました。それについてはあとで詳しく話します。
もうひとつの苦労していることは言葉が出てくるまでのスピード差です。
例えば日本でよく使う「右切れ、左切れ」、英語では「show him inside, outside」や「force him right」などと言います。こ
れらは決してそこまで難しいワードではないのですが、ほんの少し長いというだけでコンマ何秒の遅れが生じます。その間にすでに状況は移り変わり結局伝えきれずボール奪取のチャンスを逃したりすることに繋がります。
ここに関してはひたすら訓練することによって短縮されていくと思うのですが、この感覚はどうしても伝えたくて本当は熱弁したいところなのですが今回はやめておきます。
Body Language
こちらに関してはお察しの通り、世界共通なので何も変わりません。日本人と比較して外国人のほうが感情を露わにする印象でしたが、思っていたほど強烈ではありませんでした。ただ南米の人たちは予想以上に強烈でした。
英語が話せないことで苦労したこと

経験したことがある人は共感できると思いますが、その地の言葉が話せないと基本的に「アホ」だと思われます。仮に相手がそうだと思っていなくても、自分はそう感じるのではないかと思います。僕はそうでした。
これがサッカーにどう影響したかというとチームで戦術を実行するうえで「不安要素」の大きな一つとして数えられてしまうことです。
例えばセットプレーでのサインプレーで僕一人間違った動きをしたらそれがミスに繋がってしまうのです。こういった理由から明らかに簡単で明白な役割を与えられたり、キッカーを任されるのにも時間がかかりました。
そしてチームとして上手くいっていないときに、発言を求められなかったり、そこに対して信頼されていないようにも感じていました。
たしかに僕の能力上上手く伝えられないのは分かっていたのですが、「こうすれば上手くいきそうなのにな」ともやもやしながらプレーすることもたまにあり心苦しかったです。
こうした苦労を抱え続けた結果、僕のゲームコントロール力は低下したと思います。もともと大した能力ではありませんでしたが、中盤でプレーしながら全体を見渡し変化を起こすのが好きでした。その手段として会話を利用していたのですが、それをしなくなったことで変化を起こしずらくなったのはたしかです。
伝わらないからこそ得たこと
これまで英語が話せない、言語の分からない環境でサッカーをすることへの苦悩を書いてきましたが、この経験は決して悪い面ではないと考えています。特に僕にとってはあるポジティブな面をもたらしてくれました。
よく見るからこそ分かること
まず、見る力に関してです。これはサッカーに限らず私生活の時からそうでした。相手がなにを言っているかよく分からないので、相手のしたい事や考えていることをなるべく視覚的に汲み取ろうと努力していました。自然とです。
カフェで働いている時も、話しかけられた時になにを言っているか100%分からなくても、テーブルをみて「この人はコレが欲しいんだな」と汲み取るようにしていました。
これがピッチの上になると、味方や相手の状況、ピッチのスペースなど今まで以上に見るようになっていました。新しいチームでプレーするということもあり味方の状況はより一層こまかく見ていました。
特に意識していたことは「彼はいまどんなプレーをしたいのか」です。
日本であれば、上手くいかなかったシーンでもその後すぐに簡単にコミュニケーションをとって意思疎通を高めることが出来ます。その簡単であったコミュニケーションが英語となると簡単ではなくなっていました。
なのでまず、そのプレーそのプレーの瞬間に相手がなにをしたいのかよく見る。もし仮に合わなかったりしてもあとの反応を見てなにがしたかったのか考える。自分が関わるプレーの時だけでなく、どんなプレーをどんなタイミングで好むのかよく観察する。
これを習慣的にひたすら続けました。
起きた変化としてはいくつかあると考えています。
プレースタイルの変化
ひとつはプレースタイルの変化です。僕のプレーは日本にいた頃よりももっと攻撃的でアグレッシブなものに変化しました。もう少し具体的に言えば、裏に抜け出したり動き出しで相手の背後に走ることが非常に多くなりました。足が遅いにもかかわらずです。
理由としては、味方選手をよく見ることによってタイミングよく動き出せるようになったことだと思います。レベルとしてはまだまだですが確実に日本にいた頃よりは成長したところだと考えています。
この「よく見ること」で「使われるケース」が増えたというのが一つ目です。「よく見る」とパスに活きてより「使う側」になりそうですが、その逆だったのがおもしろいところです。
つぎに、スペースをより把握するようになったと思います。具体的には全体を見渡すことで、自分がいるべき場所を正しく判断できるようになってきたと思います。日本にいた頃は、話て指示をすることに使っていた労力を見ることに使うようになった分、スペースについて敏感に認識するようになったと思います。
特にボールを動かしながら、「次にどこにスペースが出来るのか」この部分が向上したことにより、よりフリーな状態でボールを受けれるようになった気がします。体感的にですがね。
さいごにまとめると、見ることによってチームメイトとの「アイコンタクト力」「イメージの共有力」「観察力」が向上しました。もともとコミュニケーションには3種類あると述べましたが、そこにアイコンタクトというコミュニケーション能力が加わった感じです。
まとめ&今後について

総括してみると、言葉が分からない中でのサッカーは苦労する事も多く少なからずハンディキャップをもってプレーしていたと思います。ですが、そのおかげ伸びた能力もあることに気付けたのも事実です。
では、この成長は日本にいたままでは味わうことは出来ないのだろうか。
この答えは分かりません。海外に来る前々からこの変化を期待して、日本を飛び出たのではありません。
でも良くも悪くも、プレースタイルが変化したことは事実です。名もキャリアもないサッカー選手が生き残るためには結果を出すしかないと自分に言い聞かせ、点を強く意識していたという理由もあると思います。日本ではパッとしなかった僕の身体的特徴やプレースタイルが、海外の環境ではレアで特徴的になっている可能性もあります。
それでも一貫して言えることは、その場で生き残るために必死にプレー(生活も)してきたということです。そして今後も常に求められるプレーは変わってくると思います。僕はそのすべてに対応していきたいと考えています。それがサッカー選手として成長し、そして人間的な成長にも繋がっていけばいいと思っていますので。
つまり、半強制的ではありましたが今回振り返った「言葉が分からない環境でのサッカーについて」も結局は僕の対応力を向上する1つのきっかけとなっていたんだなと思いました。





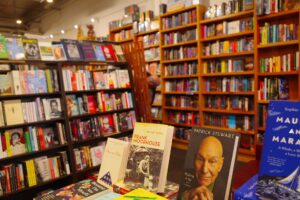



コメント